
老いをどのように生きていったらいいのでしょうか?

ちょうど今月で75歳になり、世間では、後期高齢者と言われる年齢になりました。幸い大きな病はありませんが、肉体の衰えは感じています。私は、配偶者も子どももいない人生でしたので、現在は1人で何となしに本を読んだり、散歩したり、近所に住む弟夫婦の家族と会ったりして日々を過ごしています。特に不満はありませんが、最近「このままさらに衰えて、死ぬだけなのだろうか……」と漠然とした虚しさを感じ、気力が衰えています。今さら何か趣味を持つというのも、何だか億劫に感じますし、残された人生の時間をどのように生きていったらいいのかわかりません。
75歳男性・無職
編集部より
ご相談、ありがとうございます。まずは今月お誕生日であったとのこと、おめでとうございます。「人生100年時代」と言われ、世界一の長寿国である日本に住む私たちは、誰もが何らかの形で、「老い」ということと向き合って生きてゆくことになります。ですから、「老いをどうやって生きたらいいのか」という想いは、ご相談者の方だけではなく、きっと多くの方が突き当たる疑問だと思います。
高橋佳子先生は、人間を魂として捉える永遠の生命観に基づき、「老い」に対する新しい考え方を示されています。著書の中から、ご相談に関連する箇所を一部抜き出してご紹介いたします。
老いとは、永遠の生命に1番近い季節
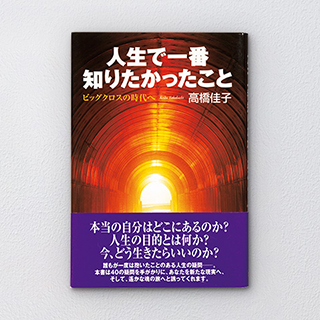
高橋佳子先生
『人生で一番知りたかったこと』より一部抜粋・要約
「老い」について考えようとするとき、私は、釈尊の歩みを心に思い浮かべます。ご承知のように、釈尊は仏教の開祖です。2500年前、インドの小国・釈迦族の王子に生まれながら、やがて一切を捨てて出家し、厳しい修行を経て、人間が抱える不安を解決するための道を見出しました。その教えの核心は、人間の力ではどうすることもできない法則——諸行無常、諸法無我——の支配する現実世界のありようを理解し、あるがままに受容するとき、人々の心には涅槃寂静(ねはんじゃくじょう、「静かな安らぎ」の意)の境地が訪れるとするものです。
釈尊の晩年は、如何ともし難いものを多く抱えた日々となりました。身近に歩みを共にした直弟子の多くを先に亡くし、従兄弟のデーヴァダッタを首謀者とする教団の混乱も収拾しなければなりませんでした。さらに追い打ちをかけるように、自らの祖国が大国コーサラ国によって滅ぼされてしまうという悲劇を受けとめなければなりませんでした。
自らの説いた教えの通り、多くのものを失い奪われ、悲しみと痛みに満ちた季節——。釈尊自身もその悲哀と孤独に向き合い、「わが齢は80となった。たとえば、古ぼけた車が革紐の助けによってやっと動いて行くように、恐らく私の車体も革紐の助けによってもっているのだ」と語っています。
しかしその釈尊が、最晩年、死の直前に残した言葉は、それとはまったく異なるものだったのです。
「この世は何と美しく、人間の命は何と甘美なものだろう」
釈尊の心には、確かにそのように映っていたということでしょう。
現実の世界が抱く厳しさと寂しさを嫌というほど噛みしめつつも、その中で、否その中だからこそ、時に対して、人に対して、そして世界そのものに対して、優しい愛情と滋味豊かな態度で接することができる——。そこに秘められた、かけがえのない「いのち」に目覚めることができる。それこそ老いを生きる私たち、老いに向かう私たちへの、言葉を超えた指針であると思わずにはいられないのです。
……確かに、老いの季節は、様々なものを私たちから奪い去ってゆきます。少し前までは夜遅くまで仕事をしていても平気だったのが、視力がおぼつかなくなり、疲れが蓄積するようになって無理がきかなくなる。よくわかっているはずのことでも、言葉がすぐに出てこなくなり、「物忘れが激しくなった」と家族からも言われる。ふと気がつくと何やら周囲のことにやけに怒りっぽくなり、頑固になっている。若い時代のみずみずしいエネルギーは衰え、中年世代のときに持っていた闘志もいつの間にか消え失せてしまった……。そんな現実に気がつくとき、人は自らに老いの季節がやって来たことを切実に感じ始めるのでしょう。
しかし、老いは、単に喪失の季節なのではありません。
老いの季節の中で私たちは、喜びも悲しみも成功も失敗も、これまでの人生で体験した一切を、さらに味わい深く受けとめることができます。善悪や好悪といった相対の次元すら超えて、もう1度大切な意味を発見し、豊かな智慧に結晶化する、人生結実の時を迎えるのです。それは本当のはたらき——「人生の仕事」を果たすときとも言えるものではないでしょうか。余生を送るというだけにはとどまらない生き方です。これからようやく、「人生畢生(ひっせい)の仕事」を始めることができるということです。
かつて体験してきた無数の出会いと出来事を何度も何度も噛みしめ、反芻して、味わい尽くしてゆくときであり、バラバラだった出会いや出来事が、1本の意味の糸によって数珠のようにつながるのを発見するとき——。無意味な出会いはなく、人は出会いによって人となることを、1人ひとりが身をもって証すときでもあるでしょう。
そして、そのように老いの季節を生きて人生を終えていった多くの方に、私は出会ってきました。身体が思い通りにならなくなっても、「ベッドの上でできることがある」と、お見舞いに来られる人や看護師さんを励まし続けて、人生をまっとうした方。70歳を超えて、今まで数十年にわたってこだわり続けてきた恨み心が晴れ、まるで人が変わったように、他人のお世話に東奔西走された方……。人間の内に宿る崇高な光に、頭を垂れ、手を合わさずにはいられない想いでした。
そうしたお1人お1人が、人間の魂は最後の最後まで成長し深化し続けるということを、現実の姿をもって如実に教えてくれたのです。それはまた、私たち人間がビッグクロス(縦の絆[大いなる存在との絆]と横の絆[永遠の生命との絆]の交差)との絆を取り戻したとき、ここまで輝いて生きることができるという姿でした。
多くの人にとって、「老い」の現実を受容することが身を切るようにつらいのは、やはり、最終的に老いの向こうに人生の終焉である「死」が見えるからではないでしょうか。
これまで当たり前のように繰り返してきた毎日の暮らしもやがて体験できなくなる。自分の存在すらなくなり、一切が無に帰してしまう。そのような虚無の淵に沈むような不安が、根底に横たわっているからだと思います。それは突き詰めて言うならば、「死んだら終わり」という基本的な人間観が、私たちの中に厳然としてあるということなのでしょう。
しかし、永遠の生命観に立つとき、私たちはその桎梏(しっこく)から解き放たれます。人間は、永遠の生命として生き通しの人生を生きる存在。だから、「死んだら終わり」ではなく、「死は新たな生の始まり」である——。もしこの人間観を、概念としてではなく、徹頭徹尾、真実として受けとめることができたならば、あなたの老いに対する捉え方、ひいては人生に対する捉え方には、コペルニクス的転回とも言うべき決定的な変貌が訪れるのではないでしょうか。
老いの季節は、次なる生に向かうために必要な智慧を集大成する準備の季節になるからです。老いとは、1つの人生を卒業し、新たな生を始めるプロセスであり、かけがえのない節目なのです。





